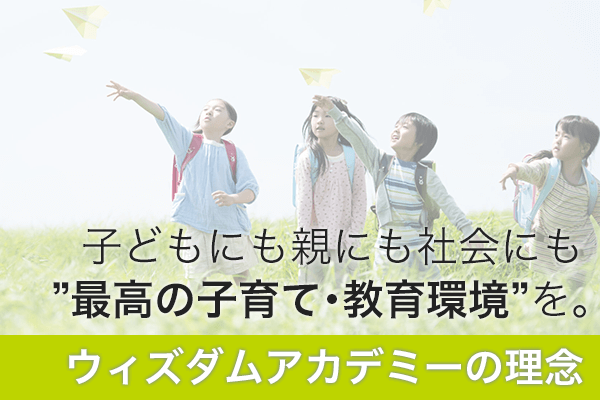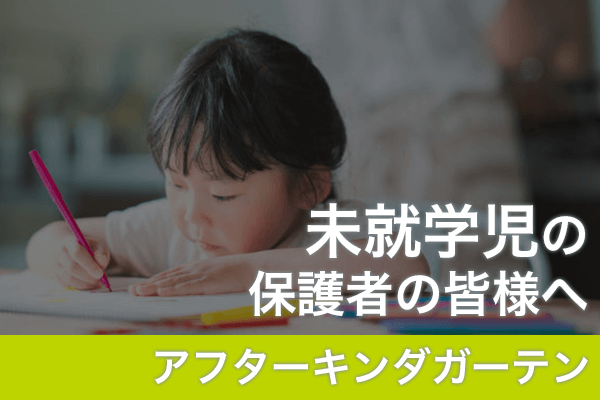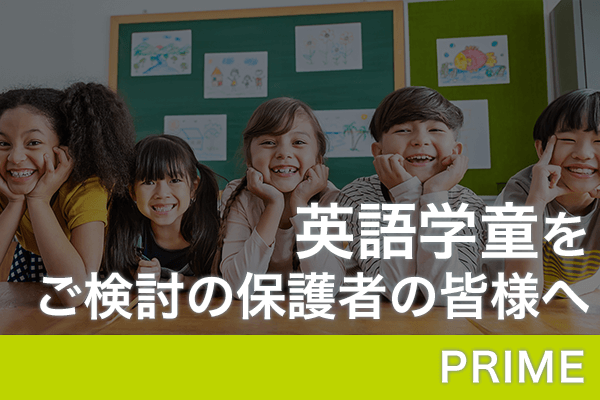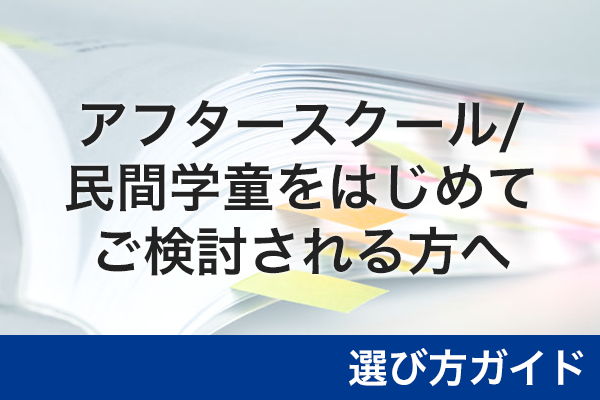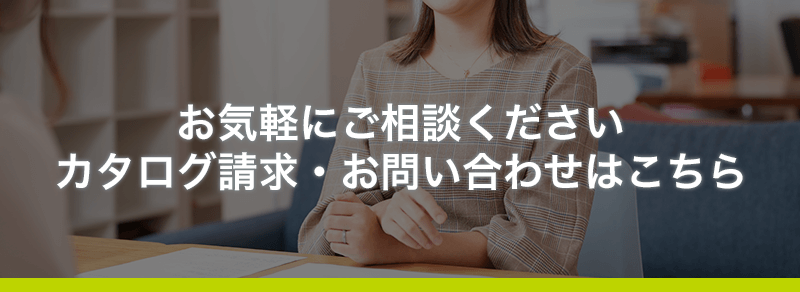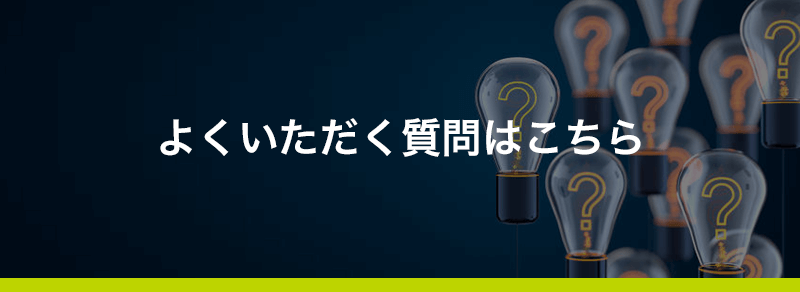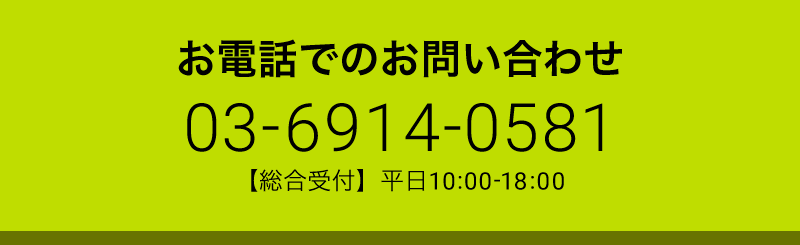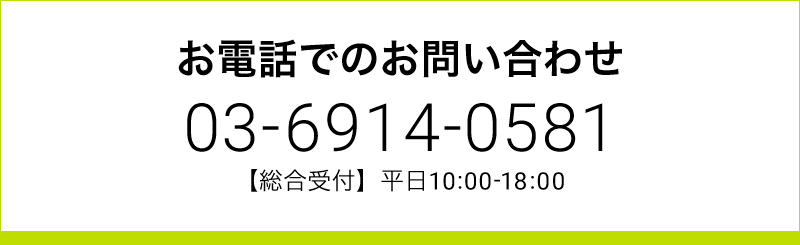幼児教育における心構えと3つの大切なこと|教育法の種類も解説

子どもを育てる上で、幼児教育の必要性や進め方は気になるポイントではないでしょうか。幼児教育と一口に言っても、具体的な内容は、教育方針や年齢によって異なります。子どもの健やかな成長をサポートするためには、幼児教育について詳しく理解することが大切です。
当記事では、幼児教育の概要・代表的な種類・年齢別の進め方・幼児教育のメリットとデメリットなどを解説します。幼児教育に関する情報を把握した上で、子どもに受けさせるかどうかを考えましょう。
幼児教育とは?

幼児教育とは、主に小学校に就学前の子どもに対して行われる教育のことであり、対象年齢に明確な定義はありません。
幼児教育の役割は、子どもに学習や人間形成の基礎を身につけさせることです。子どもが産まれてから数年間は大脳が発達し、言語能力や身体能力が急速に身につきます。この時期に幼児教育でさまざまな刺激を受けると、人間としての基礎的な能力を伸ばせると言われています。
また、幼児期は子どもの好奇心が旺盛なため、幼児教育によって得意分野を見つけることもできるでしょう。なお、幼稚園や保育園などの施設で実施される教育・指導だけでなく、家庭や地域社会における教育・体験も幼児教育に含まれます。
出典:文部科学省「第1章 子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の方向性」
早期教育との違い
幼児教育と早期教育は混同されやすいものの、目的や主体が大きく異なります。幼児教育の目的が、長期的な視点で生きる力の基礎を身につけさせることである一方で、早期教育の目的は勉強やスポーツなどの専門技能を先取りして習得させることです。小学校受験対策や入学準備のための事前学習は早期教育に分類されます。
また、幼児教育は子どもの自主性を重んじ、結果よりも学習意欲や好奇心を尊重します。一方、早期教育では保護者が主体となり、子どもに対して学習カリキュラムを提供することが一般的です。
幼児教育のメリット・デメリット

幼児教育にはメリット・デメリットがあるため、家庭で取り組む際は正しく理解しておくことが大切です。以下では、幼児教育のメリット・デメリットそれぞれについて解説します。
メリット:就学する際の土台を整えられる
幼児教育を行うと、好奇心・認知能力・身体能力などの向上が期待できます。また、新しい刺激に触れることや、学習に対する抵抗感が緩和され、就学後の環境に適応しやすくなるでしょう。
また、幼児教育で保護者や保育者と多くのコミュニケーションをとることで、就学後に先生の話を聞く姿勢が身につく可能性があります。就学する際の土台を整え、子どもに無理のない成長を促せる点が幼児教育のメリットです。
デメリット:保護者がプレッシャーを感じる場合がある
幼児教育の効果は、テストの点数のように定量化することが難しい傾向です。そのため、保護者が効果をなかなか実感できない場合があります。
子どもの将来を心配する保護者ほど、焦りやプレッシャーを感じやすい点が幼児教育のデメリットです。しかし、あくまでも子どもの自主性を尊重する必要があります。
幼児教育の代表的な種類
幼児教育には、子どもとの関わり方や保育内容が異なる複数の手法があります。幼児教育の代表的な種類は次の通りです。
- 石井式教育法
- ヨコミネ式教育法
- 七田式教育法
- モンテッソーリ教育
- ピラミッドメソッド
- シュタイナー教育
- レッジョ・エミリア・アプローチ教育
- ドーマンメソッド
- ニキーチン教育
ここからは、上記に挙げた9種類の幼児教育ごとに概要や特徴を解説します。
石井式教育法
石井式教育法は、教育学者の石井勲博士によって提唱された教育法です。思考は言葉によって形作られるという考え方を軸として、多くの日本語に触れさせることで子どもの知的能力を育みます。
絵本やカードを使って、遊びながら言葉や文字を記憶させていくことが、石井式教育法の特徴です。語彙力の強化を通じて、理解力やコミュニケーション能力を育みます。
ヨコミネ式教育法
ヨコミネ式教育法は、女子プロゴルファーの横峯さくらの伯父である横峯吉文が提唱した教育法です。「心の力」「学ぶ力」「体の力」の3つを育み、子どもたちの可能性を引き出すことを目的としています。
子どもが持つ以下の4つの心理を生かすことが、ヨコミネ式教育法の特徴です。
- 競争したい
- 真似をしたい
- 少し難しいことをしたい
- 認められたい
読み書き、計算、体操、音楽、図工など、さまざまな活動に取り組む中で、子どもたちが自立して生きていく力を身に付けられるようサポートします。
七田式教育法
七田式教育法は、日本の教育研究科の七田眞が提唱した教育法です。子どもの脳が0~6歳の幼児期に大きく発達することを踏まえ、右脳教育を積極的に取り入れます。
フラッシュカードトレーニングや暗唱、指先の運動などに重点を置くのが七田式教育法の特徴です。併せて「認めて・褒めて・愛して・育てる」をキーワードに豊かな心を育むことで、子どもたちが将来大きな夢や志を持ち、リーダーシップを取れるよう導きます。
モンテッソーリ教育
モンテッソーリ教育は、医学博士で教育専門家のマリア・モンテッソーリによって提唱され、100年以上支持されてきた教育法です。子ども自身が持つ自己教育力を前提に、子どもの自主性や創造力を高めます。
独自の知育教材や環境作りによって子どもの好奇心を引き出すことが、モンテッソーリ教育の特徴です。教育者は子どもの年齢に応じて適切な支援を行います。
ピラミッドメソッド
ピラミッドメソッドはオランダの政府教育評価機構Citoによって提唱された教育法です。子どものやる気や保育者の主体性など、4つの基礎概念がピラミッド型に構成されています。
子どもが安心できる環境で、想像力や自己解決能力をバランスよく育てることがピラミッドメソッドの特徴です。また、ピラミッドメソッドは保護者が個性の重要性に気づき、子どもに対して良い影響を与えることも促します。
シュタイナー教育
シュタイナー教育は、哲学者ルドルフ・シュタイナーが提唱した、100年以上の歴史がある教育法です。子ども一人ひとりの個性を尊重し、能力を最大限に発揮させることを目的としています。
人間の成長を7年ごとに分割し、各時期に合わせた教育を実践するのがシュタイナー教育の特徴です。学力よりも人間形成に重きを置き、体・心・頭のバランスが取れた大人に成長できるよう支援します。
レッジョ・エミリア・アプローチ教育
レッジョ・エミリア・アプローチ教育は、第二次世界大戦後にイタリアのレッジョ・エミリアという小さな町で生まれた教育法です。子どもの個性を尊重し、自由な表現力やコミュニケーション能力、探求心、考える力などを引き出すことを目的としています。
グループを作って共同作業を行い、話し合いをしながら物事を決める経験を積み重ねることがレッジョ・エミリア・アプローチ教育の特徴です。また、保育施設での様子を写真・動画・音声として残し、教材とします。
ドーマンメソッド
ドーマンメソッドは、グレン・ドーマン率いるアメリカの人間能力開発研究所が生み出した教育法です。脳に障害がある子どもたちのための研究が元になっており、日本の幼児教育で重視される知育にもよいと言われています。
人間の脳が最も成長する時期と言われる0~6歳の間に、五感や運動を通して子どもたちの脳に適切な刺激を与えるのがドーマンメソッドの特徴です。刺激によって脳の発達を促し、適切な理解力や判断力を付けることを目的としています。
ニキーチン教育
ニキーチン教育は、ロシアのモスクワに住んでいたニキーチン夫妻が提唱した教育法です。子どもたちの能力を最大限に引き出すことや、自分で課題を解決する力、思考力などを養うことを目的としています。
子どもを信頼し、多少の危険が伴っても難しい課題や困難に挑戦させるのが、ニキーチン教育の特徴です。代表的な取り組みである積み木遊びでは、子どもに見本と同じ図形を作ってもらい、正解したら大げさに褒めることで成功体験を与えます。
幼児教育を実施するときの心構え
幼児教育は、取り組み方を誤ると子どもの発達に逆効果となる恐れがあります。そのため、保護者は幼児教育を実施するにあたって、いくつかの心構えを念頭に置いておくことが大切です。
幼児教育で大切な心構えとしては、以下の4点が挙げられます。
親の希望を押しつけない
幼児教育では、親の希望を子どもに強制しないことが大切です。子どもが関心を持っていない遊びや勉強を無理やり押しつけても、楽しく取り組むことができません。
子ども自身が楽しみを感じられない場合、幼児教育の目的である好奇心や自主性が育まれない可能性があります。子どもの行動や興味対象によく気を配り、子どもを主体として幼児教育に取り組みましょう。
子どもが達成感を味わえるように配慮する
日々の生活の中で、「頑張ったね」「よくできたね」などの言葉をかけると、子どもは達成感を味わえます。達成感は子どもの自信や自己肯定感を高めるために重要です。
教育や指導を行うときだけでなく、遊びや食事などの日常的なシーンでも、可能な限り多くの機会に子どもが達成感を味わえるように配慮しましょう。
親子で一緒に楽しむようにする
「幼児教育は子どもが中心」というイメージを持っている方も多いでしょう。しかし、幼児教育の効果を向上させるためには、親子で一緒に楽しみながら学んでもらうことが大切です。子どもにとっては「親と一緒に楽しんだ」という事実が喜びにつながり、興味の幅を広げるきっかけになります。日常生活の中でも親子で取り組める幼児教育は多いので、子ども自身の性格や興味の方向性などを考慮しながら挑戦しましょう。
家庭で手軽に取り組める幼児教育としては、絵本の読み聞かせやお絵描き、ボール遊び、ブロック遊びなどが挙げられます。また、お片付けや家事の一部の手伝いを頼むのも立派な幼児教育です。簡単な課題からスタートし、成功体験を積み重ねることで子どもは自信をつけ、さらなる挑戦や成長につながりやすくなります。
子どもの成長に応じた教育方法を実施する
一口に子どもと言っても、できることは年齢によって大きく異なります。子どもは発達段階ごとにおおむね共通する特徴を持っており、特徴を踏まえた成長をそれぞれの段階で達成することが理想的です。家庭で教材や知育玩具を利用した幼児教育を行う場合は、子どもの年齢に合ったものを選ぶとよいでしょう。
ただし、同じ年齢の子どもであっても、成長過程は人によってさまざまです。そのため、子ども一人ひとりの成長に応じた教育方法を実施する必要があります。
出典:文部科学省「3.子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題」
【年齢別】幼児教育の進め方

幼児教育の進め方は年齢によって異なるため、子どもの発達段階に合わせて教育の方法を変えることが重要です。特に、1歳・2歳・3歳の子どもには、それぞれ適切な教育方法があります。
各年齢の子どもに見られる特性や、優先的に取り組むべき教育内容は次の通りです。
【1歳】脳に刺激を伝える
1歳は、子どもが声を聞き分けられるようになり始める年齢です。また、周囲の様子を見たり、手で触れて確かめたりすることで認知能力が発達します。
そのため、1歳の子どもに対する幼児教育では、五感を通じた刺激を脳に与えることが重要です。さまざまな刺激に触れさせることで、子どもの感覚や思考力を発達させられます。
また、イラストが描かれたカードを使って言葉を聞かせる教育や、絵本の読み聞かせなども効果的です。教育の場は屋内に限らず、屋外で植物や動物を指さしながら名前を教えることも子どもの発達を促します。
【2歳】社会性を身につけさせる
2歳は、自分と周囲の区別がつき始め、自我が芽生え始める年齢です。子どもが反抗期(イヤイヤ期)に入り、親の言うことを聞かなくなる場合もあります。
反抗的な態度は自我が芽生えた証拠でもあるため、子どもを尊重しながら丁寧に幼児教育を進めることが重要です。社会生活の基本的なルールを少しずつ学ばせましょう。また、年齢の近い友達と遊ぶ経験を通じて社会性を身につけさせると、後により大きな成長が期待できます。
2歳の子どもには、1歳の頃よりも複雑な刺激に触れさせることもポイントです。シールや積み木、紐通しなど指先をたくさん動かす遊びを取り入れましょう。赤・青・黄色など基本的な色に触れる活動も効果的です。
【3歳】身の回りのことを覚えさせる
3歳になると、食事や着替えなど基本的な生活を自分でできるようになり始めます。身の回りのことを認識できるようになった段階で、子ども自身に挑戦させると効果的です。
なお、失敗したときに叱ったり、保護者がすべてを代わりにやったりすることはできる限り避けましょう。手本を見せた上で挑戦させると、自分の力で達成できたという自信につながります。
また、これまでより難しいパズルで遊ばせたり一緒に絵本を読んだりすると、好奇心や集中力を育むことも可能です。加えて、3歳は文字や数字に触れさせるタイミングでもあります。ただし、子ども自身の興味や発達に合わせて、教材や知育玩具を選ぶことが大切です。
幼児教育における3つの大切なこと

幼児教育の効果を適切に得るためには、以下のポイントを押さえることが大切です。
- 遊びを通して学びを得ること
- 親が環境を作ってあげること
- 子どもが自ら考える力を育むこと
幼児教育における3つの大切なことについて、それぞれ詳しく解説します。
遊びを通して学びを得ること
子どもにとっては遊ぶことが仕事であり、遊びを通してさまざまな経験をする中で、何かを考えたり感じたりしながら成長します。幼少期の遊びの体験は、集中力や創造力、やり抜く力など、さまざまな非認知能力を育む鍵です。
一昔前は、遊びが子どもに悪影響を与えるとされ禁止されるケースもありましたが、現在では遊びの重要性が再認識されています。実際に、今の日本の保育園や幼稚園では、必ず遊びの時間が確保されています。子どもが自分の意思で関心をもって活動するきっかけになり、その後の人生における学習意欲の基礎を作るのが遊びです。幼児教育においては、多くの体験を通して楽しさや達成感を知ることが大切と言えます。
親が環境を作ってあげること
幼児期の子どもは、自分で環境を作ったり、変えたりすることはできません。そのため、親が教育環境を作ってあげることが大切です。
幼児教育における「環境」とは、主に以下の3つを指します。
| 人的環境 | 誰がどのように関わるのかという観点です。子どもと大人が信頼関係を築き、子どもが安心して遊びに取り組める状態を目指します。親子だけではなく、子ども同士や地域社会との交流も重要なポイントです。 |
|---|---|
| 物的環境 | けがをする可能性を極力排除した空間作りや、遊びに集中できる場所、発達段階に適したおもちゃを用意することなどが挙げられます。 |
| 自然的環境 | 動物や植物といった自然と触れ合える機会を用意することも重要です。屋外の自然だけではなく、自宅で家庭菜園を始めたり、自然素材のおもちゃを家に置いたりといったことも含まれます。 |
子どもが自ら考える力を育むこと
教育の目的は、知識の量を増加させることではなく、自分自身で何かを見つけ、創造する力を養うことです。
かつては学力を確かめる方法として知識を求める傾向があり、詰め込み教育がメインでした。しかし最近では、与えられる知識をただ記憶するだけの学習はあまり必要とされなくなり、子どもの考える力を伸ばすことに重点が置かれるようになりました。知識や学力といった目に見える力だけではなく、学習へのやる気や根気そのものの大切さが重視されています。
考える力は、子どもたちが将来、自分の人生を自分の力で歩んでいくために必要なものです。これから社会がどのように変化しても、自発性をもって課題を解決し、自分で判断して行動できるよう育成することが重要と言えます。
まとめ
幼児教育とは、主に未就学児を対象とした教育全般を指す言葉であり、子どもの年齢によって幼児教育の適切な方法は異なります。
幼児教育のメリットは、子どもの自主性を育み就学する際の土台を整えられることです。親の希望を押しつけず、子どもが達成感を味わえるような配慮を行いましょう。
幼児教育を視野に入れた子どもの預け先をお探しの際は、民間学童保育「ウィズダムアカデミー」のご利用を、ぜひご検討ください。ウィズダムアカデミーは3歳からのお預かりが可能で、30種類以上の豊富な習い事・教育サービスを提供しております。