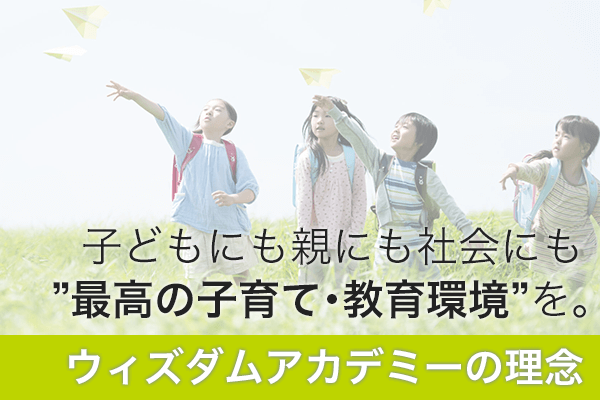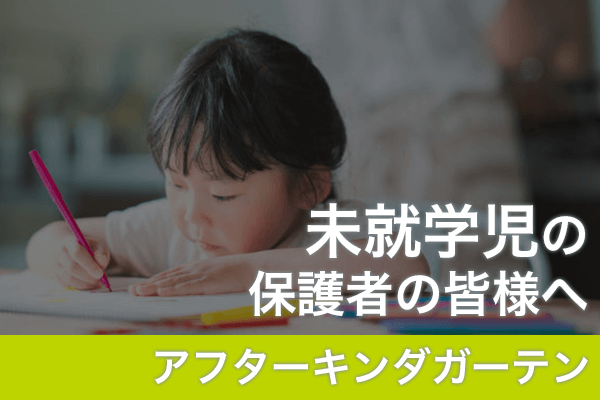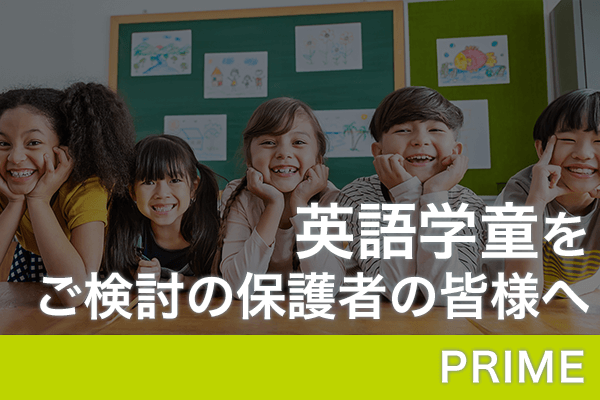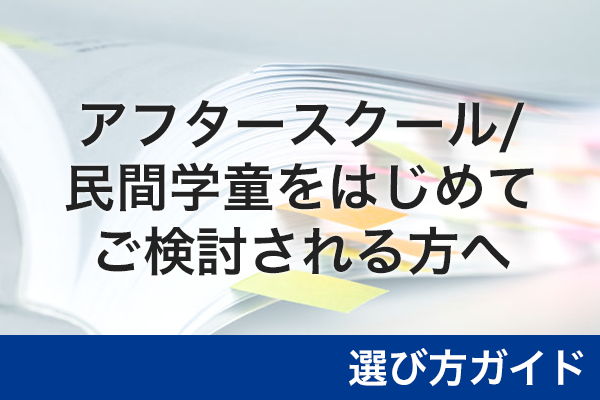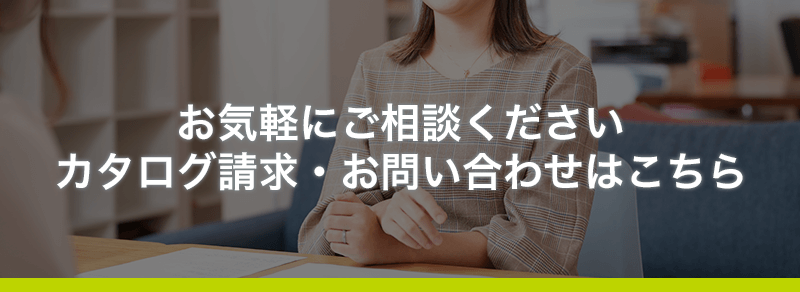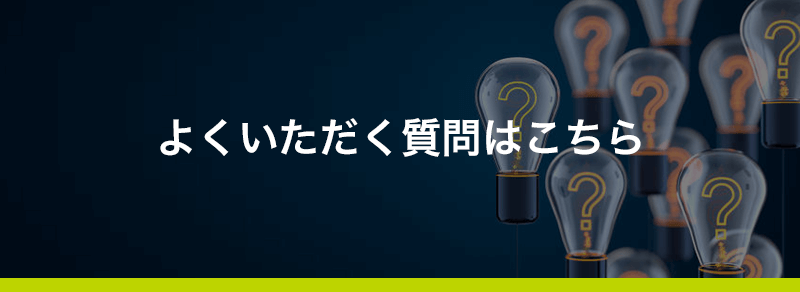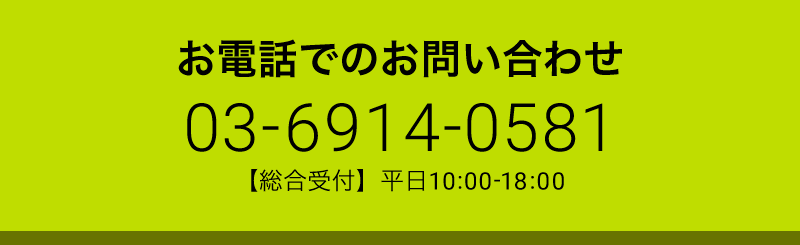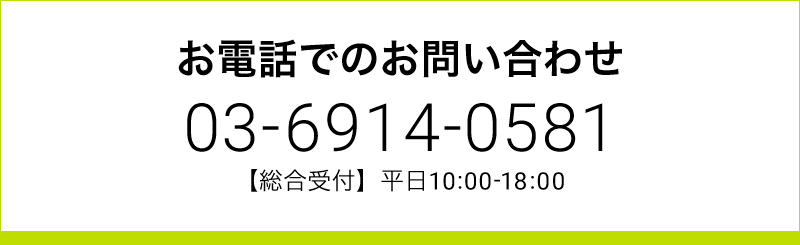保育園は何歳まで利用できる?入園させやすい時期や幼稚園との違いも

「育休が終わったら元の職場に復帰する」「育児と仕事を両立したい」などの理由で、子どもを保育園に入園させたい家庭も多いでしょう。保育園は保護者に代わって乳幼児の保育を行う施設ですが、何歳から何歳まで利用できるのでしょうか。
当記事では、保育園を利用できる年齢をはじめ、保育園の特徴や幼稚園との違いなどを解説します。保育園に入園させやすいタイミングや保育園に入園するまでの流れを確認し、スムーズに入園できるよう計画を立てましょう。
保育園は何歳まで利用できる?幼稚園との違いも解説

保育園の利用対象となる子どもの年齢は、「0歳から小学校入学前(満5歳となった年度の3月末)まで」が一般的です。園によっては入学式の直前まで預かり保育をしている場合もありますが、基本的には小学校に入学する前の3月まで利用できると考えておきましょう。
利用年齢の上限が定められている一方で、保育園に入園できる年齢・月齢の下限は一律に定められているわけではありません。「生後8週以降」など産休明けに預けられる施設もあれば、「首がすわってから」「満1歳から」といった施設もあるため、事前に確認することが大切です。
なお、幼稚園は保育園と同様に小さな子どもが通園する施設として知られていますが、利用できる年齢など特徴に違いが見られます。
保育園と幼稚園の違い
保育園
| 施設の特徴 | 厚生労働省の管轄であり、保護者の就労などで保育に欠ける乳幼児の保育を保育士が行う ※就労などの理由がある家庭が優先して入園できる |
|---|---|
| 対象年齢 | 0歳~小学校入学前 |
| 保育時間 | 7時30分ごろ~18時ごろまで ※延長保育ができる施設もある(標準保育時間…8時間) |
| 保育料 | 世帯収入によって決まる |
| 保護者の負担 | 共働き家庭が多いため、PTA活動など親が送迎以外に園に出向くことが少ない 給食があるため、基本的にはお弁当を用意しなくてもよい 年末年始やお盆期間は預かりがない場合もあるが、小学校のような長期休みがない |
幼稚園
| 施設の特徴 | 文部科学省の管轄であり、就学前の教育を幼稚園教諭が行う ※誰でも入園可能 |
|---|---|
| 対象年齢 | 満3歳~小学校入学前 |
| 保育時間 | 9時ごろ~14時ごろまで ※延長保育ができる施設もある(標準保育時間…4時間) |
| 保育料 | 公立の場合は市区町村が、私立の場合は園が決定する |
| 保護者の負担 | PTA活動や保育参観、バザーなどの行事が多く、親が園に出向くことも多い お弁当持参の園もある 長期休みがある(※預かり保育がある園も多い) 私立幼稚園であれば園内で習い事ができる場合もある |
以上のように、保育園と幼稚園は主に対象年齢や保育時間、保護者負担などの観点で大きく異なります。保育園と幼稚園との違いを理解した上で、利用者(パパ・ママ)の状況や子どもに合った施設形態を選ぶようにしましょう。
保育園に入園させやすいタイミング

保育園は0歳からでも入園可能であり、持ち上がりの少ない「0歳の4月」が入園しやすいとも言われています。しかし、0歳代は月齢や個人によって発達状況が大きく異なります。子どものタイプや入園するときの月齢によっては、0歳代での入園がベストなタイミングとは言えません。
ただし、1歳からの入園を目指そうとすると、育休(育児休業)が終わって職場復帰する保護者が多くなるため、競争率が高くなる場合があります。0歳クラスからの持ち上がりで定員が埋まる可能性もあるため、入園を希望する地域の保育園事情を十分に調べておく必要があるでしょう。
0歳の4月以降では、子どものコミュニケーション能力や運動能力がある程度発達している3歳前後が保育園に入園させやすいタイミングと言われています。3歳児クラス(年少クラスにあたる学年)は保育園での受け入れ人数も増えるため、入園先で悩むことも少ないでしょう。
保育園に入園するまでの流れを6ステップに分けて解説!

保育園に入園するには、保育園に関する情報集めや園見学、入園の申し込みなどを適切な時期・流れで行う必要があります。
入園の流れは、保育園の方針や施設の種類によって異なる部分もあります。保活や入園準備をスムーズに進めるために、保育園を見学した際などに園に直接聞いておくとよいでしょう。
ここでは保育園に入園するまでの一般的な流れを紹介します。基本的な流れと各ステップで行うべき内容を確認し、ポイントを押さえた入園準備を行いましょう。
STEP1|保育園の見学
希望する地域の保育園に関する情報をある程度集めたら、気になる保育園に行って施設の中を見学しましょう。実際に保育園を見学すると、園の保育環境や保育観、施設の雰囲気、先生や園児の様子を確認できます。質問があれば、見学時に園の先生に直接尋ねてみてください。
保育園の見学時期は、入園申込の2〜3か月前に済ませておくと、保育園選びについてよく考える時間を十分に取れます。入園申込の時期から逆算してスケジュールを調整し、保育園に見学の予約を入れておきましょう。
STEP2|提出書類の準備と提出
認可保育園に入園を申し込むには、居住地の市区町村に必要書類を提出する必要があります。主に下記のような書類が必要となるため、自治体に確認した上で書類の準備を進めましょう。
■認可保育園への入園申込で必要となる主な書類
- 保育施設利用申込書
- 家庭状況申告書
- 勤務証明書(就労証明書)など(保育を必要とする理由を証明できる書類)
- 提出書類確認表
自治体にもよりますが、4月入園を希望する場合、前年の10〜12月ごろに入園申込期間が設けられていることが一般的です。他の月に入園したい場合は、希望月別に受付期間が設けられているため、自治体に確認した上で申請手続きを進めてください。
STEP3|面接
申込希望園の定員に空きがあれば、基本的には希望の保育園に入園できます。ただし、待機児童の多い地域であったり、人気のある保育園に入園を希望したりする場合は、入園希望者数が定員オーバーになることも珍しくありません。
入園希望者数が保育園の定員数を上回った場合、自治体によって利用調整の選考・審査が実施されます。書類選考や電話で確認のみの自治体もありますが、場合によっては面接をすることもあるため、保育園に入園する必要性などを適切に説明できるようにしましょう。
STEP4|入園内定通知
4月入園を希望する場合、その年の1〜2月ごろに郵送で結果通知が届くことが一般的です。結果がなかなか届かない場合には、自治体に連絡して相談します。
入園内定通知を受け取った場合は、入園に向けての準備を進めていく必要があります。入園許可が下りなかった場合は「空きがある保育園を探す」「認可外保育園や小規模保育、保育ママなどに申し込む」「次のタイミングを待つ」などの選択肢も検討しましょう。
STEP5|健康診断
入園の内定を受けたら、保育園からの案内にしたがって入園準備を進めます。保育園の先生との面談や説明会・健康診断への参加もあるため、保育園の日程に合わせてスケジュールを空けておきましょう。
入園前の健康診断は、一般的に保育園のかかりつけ医(園医)が担当します。保育園生活中に園児がケガや病気をした場合、保育園の先生は園医に対応を相談したり、診察を依頼する場合があります。健康診断を受ける際には、園医についても確認しておきましょう。
STEP6|入園手続き
入園前の面接や健康診断を問題なくクリアできれば、保育園への入園が確定します。入園予定の保育園で使用する用品を購入・作製したり、自身の復職準備や求職準備をしたりと、新しい生活環境への準備を進めましょう。
また、入園直前には毎月の保育料の金額も確定します。世帯年収や居住地、子どもの年齢などによって金額は異なるため、必ず確認しましょう。
まとめ
保育園は0歳から小学校入学前の子どもが入園できる施設であり、「利用できる年齢の幅が広い」「主に保育が行われる」「保育時間が長い」といった点で幼稚園とは異なります。それぞれの特徴をふまえた上で、子どもや家庭に合った施設を選びましょう。
保育園に入園させやすいタイミングは一般的に「0歳4月」と言われていますが、保育園での受け入れ人数も増える「3歳」での入園もおすすめです。保育園に入園するには、必要書類の提出のほか、見学や面接、健康診断などさまざまなステップを踏む必要があります。取り組むべきことを事前に把握し、入園準備をスムーズに進めましょう。
お子さまの放課後の過ごし方を
ご検討中の皆様へ
ウィズダムアカデミーでは、民間学童・アフタースクールとしてはもちろん、定番〜人気の10-20の習いごとも受講可能です。
下記ページ「はじめてのアフタースクール選び方ガイド」ではウィズダムアカデミーのサービスだけではなく、
お子さまにどのように放課後を過ごしてほしいのかを念頭に置いて、学童・アフタースクールを選ぶ方法をご案内します。